
ピンク:帰宅困難区域
グレー:避難指示が解除になった地域
グリーン:避難指示解除準備区域
オレンジ:居住制限区域
後援会旅行で南相馬市の帰宅困難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域の外側などまわりました。
わたしは臨時会のため東京に戻りましたが、後援会の人たちがしっかり視察してきたので写真をご紹介します。
案内は「相馬新地・原発事故の全面賠償をさせる会」の村松孝一さん。
「避難指示が解除されても、病院もなく商店もない街で暮らしていけないと、約2割の人しか帰宅していない」
「家のまわりや田畑は除染できても、木の生えた山や斜面などは除染できない。そのため山の近くでは放射線量が高い」
といったことを説明してくださいました。
参加した人たちからは「原発事故から6年が過ぎても時間が止まったような町並み、耕されることなく雑草が生い茂る田畑、希望の牧場などに胸が痛んだ」という感想が聞かれました。

除染作業で削った汚染土などの放射性廃棄物を詰めたフレコンバッグが積み上げられている

除染のために表土を剥いだ所に撒くための土を削っている

除染後の土地に撒くための土を削り取られた丘。しかし、こういう赤土は栄養分に乏しいため農地に撒かれても農耕に適さない。深いところにある黒土と混ぜて肥沃な農地にしていくには長い年月がかかる

土を運ぶトラックが列をなす。堤防のかさ上げにも利用されるため、あちこちの山が削られている

利用困難になった農地に設置されたソーラーパネル。先祖代々の土地を孫子の代に繋いでいきたいという思いに支えられている

フレコンバッグが積み上げられた仮置き場。このまま中間貯蔵施設が決まらず、ここが最終置き場になることを地元の人々は恐れている

南相馬市の小高区と浪江町の境にある「希望の牧場」。国の殺処分に抵抗した吉沢さんにより運営される

「希望の牧場」。牧場主の吉沢さんはご自分の牛だけでなく他の牧場や迷っていた牛も預かって育てている

牧場主の吉澤正巳さんによる怒りに満ちたお話を聞く後援会の人たち

約300頭いる牛の飼料代だけでも年間一千万円かかるため、吉澤さんはこの宣伝カーで全国に出かけ支援を訴えているとのこと

「希望の牧場」から浪江町の帰宅困難地域に向かうバスの中では放射能測定機が毎時0.357μSv(マイクロシーベルト)に。(被曝限度線量は年間1mSvμ。SvはmSvの1000分の1)

放射線量は0.757μSv/h。東京などでは0.025μSv/h位が一般的な数値

「相馬新地・原発事故の全面賠償をさせる会」村松さんの説明で佐藤さんのお庭を見学

除染済みのため赤土と砂利が敷き詰められている佐藤さんのお庭

放射線量は0.621μSv/h。これでも国は「安全だから戻ってこい」と避難指示解除

避難指示が解除されても戻ることができず荒れ果てたままの佐藤さん宅

東日本大震災が起きた2時46分頃を差したまま止まった佐藤さん宅の時計

割れた窓からイノシシが入り込み、押し入れから布団を引っ張り出して寝床にしていたという

佐藤さん宅の裏山に行くと放射線量が0.824μSv/hに

橋を渡り裏山に入ると、放射線量が2.5μSv/hといきなり上がる。これは山の斜面などは除染作業ができないため

小川の左側が佐藤さんの敷地。右側が裏山。佐藤さん宅の周辺をいくら除染しても、除染していない山からの影響で放射能に汚染された落ち葉やホコリなどが流れこんでくる

除染済みの農地。去年は放射能を吸収すると言われヒマワリを植えたが効果がなかったため、今年は景観を美しくするためにコスモスの種を撒いたそう

バスの中でも放射線量が3.254μSv/hにまで上がるスポットが。福島第一原発が爆発した時、放射能が風に乗って通過した地域ではこのように放射線量が高いスポットが残る

浪江町、0.399μSv/hと表示されている原子力規制委員会のモニタリングポスト。しかし、線量計を当てると0.63μSv/hだった

除染したという民家前の庭では6.308μSv/h。これで「汚染は減った、帰れ」と言うのか















































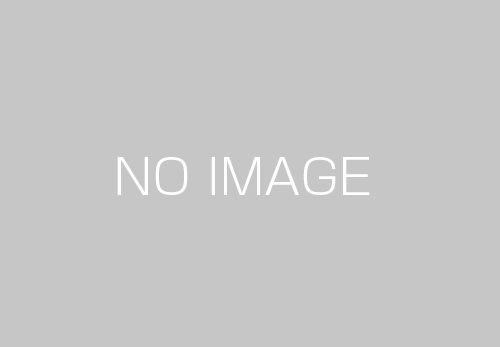

この記事へのコメントはありません。